皆さんこんにちは。
大阪府堺市の水処理会社、株式会社エスプラントサービスです。
私たちは、関西を中心に排水処理設備の保守・修繕をはじめ、関連する電気・配管・計装工事なども一貫して対応しております。
今回は、機械整備において重要な、オーバーホールについて詳しく解説していきます。
オーバーホールを適切に実施すれば、機器の寿命を延ばしたり、精度が回復したり、新たな危機を導入せずに済むという経済的なメリットも!
そのほかにデメリットや、修理・メンテナンスとの違い、オーバーホールを行う適切なタイミングなどについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
■オーバーホールとは?修理やメンテナンスとは違う?

オーバーホールとは、機械や装置などを細かく分解して行う大規模な点検のことをいいます。
機械の健康診断とも呼ばれ、日常的に実施するメンテナンスや修理とは異なり、設備を細かく分解して洗浄したり、劣化した部品を交換したり徹底的に点検します。
英語では「overhaul」と表記し、専門誌などでは「OH」と略されることもあります。
オーバーホールを行うには手間や労力がかかりますが、適切に実施することで、設備の寿命が延びたり、精度が回復するなどの効果が期待できます。
オーバーホールは、時計や車、バイク、楽器など、さまざまな機械製品に対して行われますが、今回は設備点検に焦点を当てて解説しています。
では次に、修理やメンテナンスとはどう違うのかを見ていきましょう。
修理との違い
オーバーホールと修理の大きな違いは、故障の前に行うかどうかという点です。
修理は基本的に故障した後に行います。修理の目的は、機能しなくなったものを再度役割を果たせるように直すことです。
一方、オーバーホールは故障する前に行います。オーバーホールの目的は、現在機能しているものが継続して役割を果たせるようにすることです。
メンテナンスとの違い
オーバーホールとメンテナンスの違いについても見ていきましょう。
その大きな点は、点検の規模や頻度にあります。
どちらも、故障を防止するための予防保全であることに変わりありませんが、頻度や工数が大きく異なります。
一般的にメンテナンスは、部分的な修理や点検のため、日常的に行います。設備の規模や特性にもよりますが、メンテナンスは毎日行うこともあります。
それに対してオーバーホールは、日常的にはできないような項目まで細かく点検します。
オーバーホールを一回行うには大きな労力とコストが必要であるため、メンテナンスのように頻繁には行えません。
オーバーホールと設備保全
設備保全は大きく「事後保全」「予防保全」「生産保全」「改良保全」の4つに分類され、オーバーホールは先述の通り「予防保全」に該当します。
その他保全の目的や方法は以下となっています。
-事後保全
機械や設備に故障や不具合が発生した後に、修理や部品交換などの保全対策を行う方法です。トラブルが発生するまで特別な対処を行わないため、初期投資を抑えることができます。
-予防保全
設備や部品の故障を未然に防ぐために、定期的に保全を行う保全方法です。部品ごとに耐用年数や耐用時間を定めておき、一定期間使ったら故障していなくても交換するなど、計画的に保全を行います。
-生産保全
工場の設備を導入してから廃棄するまでのサイクルにおいて、設備の生産性を高めながら維持コストを低く抑えるための保全方法です。生産保全を適切に行うことで、ラインストップや生産遅れや不良発生を防止し、適正な製造原価を達成することができます。
-改良保全
設備が故障した際に、その原因を究明して、同じようなトラブルが再発しないように設備を改善するのが改良保全です。設備の寿命を延ばすための設計改善や、修理や点検の手間を省くための設備改善などを行います。
事後保全は、故障が起きてからの対処法なのに対し、予防保全・生産保全・改良保全は故障が起こる前に対処します。
一見、故障を予防する保全方法のほうが優れているように感じますが、事後保全には予防にコストがかからなかったり、そのまま寿命まで設備を利用できることがあるといったメリットがあります。
しかしやはり予防ができていないため、予期せぬタイミングで設備を止めてしまう可能性は否定できません。このような恐れから、予防保全であるオーバーホールを適期に行うことが好まれる傾向にあります。
■オーバーホールを行うメリット
予防保全として、日常的なメンテンナスに加えてオーバーホールを行うメリットは、次のようなものがあります。
・設備の寿命を延ばすことができる
・精度を回復させることができる
・故障の可能性、故障によるコストを低減できる
・機械設備の停止をメンテナンス時に抑えることができる
・常に効率的な運転を維持することができる
コスト低減
オーバーホールを行うことで設備や機器の寿命が延び、設備交換などにかかるコストを低減できる可能性が高まります。
設備交換にかかるコストを抑制できることによるメリットを一番受けやすいのは、高額な設備や機器です。
一般的に、設備が高額になればなるほど、故障による経済的な損失は大きくなります。
オーバーホールを実施すれば、故障や停止の回数を低減できる可能性が高まるため、設備交換にかかるコストを抑えることができます。
使い慣れた設備で効率を維持しながら運転できる
使い慣れた設備から新しい設備へ変更すると、システムの仕様や使い方が変わるため、覚えなければならないことが増えたり、仕様がわからず効率や生産性が低下してしまうという恐れがあります。
オーバーホールにより設備の寿命が延びれば、使用するシステムの変更は最小限で抑えられるため、使い慣れた設備で効率よく運転を続けることが可能になります。
これにより、設備担当者が覚えるべきことが減り、教育にかかるコストの低減にも繋がります。
■オーバーホールを行うデメリット
たくさんのメリットがあるオーバーホールですが、デメリットがないというわけではありません。オーバーホールを実施することで、以下のようなデメリットを被るケースもあります。
作業に時間がかかる
オーバーホールは設備を部品レベルまで分解し、洗浄やパーツ交換を行うため、作業に時間がかかります。設備の規模や、部品の在庫の有無によって異なりますが、数ヵ月かかるというケースもあります。
日常的なメンテナンスのような短時間作業ではく、設備を長時間停止することにより被る経済的な損失を考え、オーバーホールを行う時期やタイミングには注意が必要です。
想定以上にコストがかかる
オーバーホールを行う際、部品の交換や大規模な洗浄が必要となると、コストが想定より高くなる場合があります。
その洗浄方法や部品が特殊なものとなると、よりコストがかさんでしまうケースも。
予算が限られている場合は、全ての工程を足し合わせた見積もりを取るようにしましょう。
実現困難なケースがある
必要な部品の生産が終了していたり、業者に必要な技術力がなかった場合、そもそもオーバーホールを実施できません。また、想定以上に工期が長く、生産ラインを止めておける期間を超えてしまう場合も実施できません。
古い設備や、特殊な部品を必要とする機器をオーバーホールする場合、まずは施工業者が対応可能か確かめるのがよいでしょう。
■適正頻度は4~5年に一度
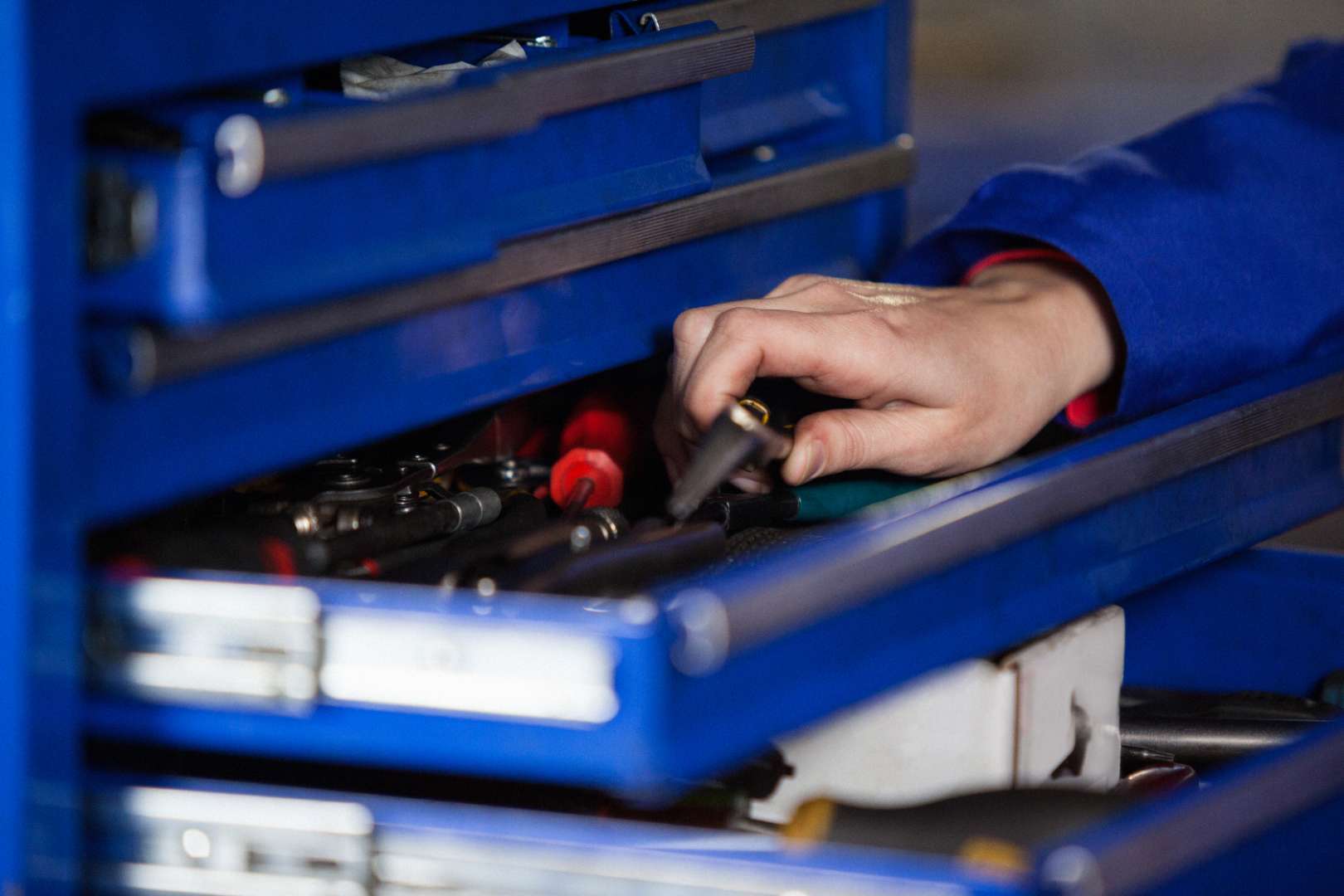
設備の規模や種類にもよりますが、オーバーホールは4~5年に一度行うのが一般的です。
比較的安易に分解できたり、機器が古いなどの場合は、3年ごとに行うこともあります。
オーバーホールを検討されている場合は、前回の実施から4年ほどを目安にしてみてください。
また、4~5年経っていなくても精度が落ちてきたなと感じたら、オーバーホール実施のタイミングと考えられます。
劣化した部品の交換や、機器内部のゆがみ調整を行うため、オーバーホール後は基本的に精度は向上します。
日常的なメンテナンス・整備も重要
オーバーホールの実施にはたくさんメリットがありますが、先述の通り大きなコストと時間を要します。そのため、普段からオーバーホールを頻繁に実施しなくてもいい状態を保つことが望ましいです。
そこでやはり重要なのが、日常的なメンテナンスや整備です。
大規模な設備の場合、いずれオーバーホールは必要になりますが、コストを抑えるためにも日常的なメンテナンスや整備を意識されることをお勧めいたします。
■適切なオーバーホールは経済的なメリットにつながる!

オーバーホールを適切に行うことにより、様々なメリットを受けることができます。
コストや時間を要する場合もありますが、長期的な目で見ると結局はコストダウンにつながる場合がほとんどです。
予防保全を行っている設備をお持ちの場合は、ぜひオーバーホールも検討してみてください。
私たちエスプラントサービスは、関西を中心に水処理設備の保守点検をメインに対応しております。設備の保守点検を行っていると、必然的に電気工事や配管工事など、一定量の工事案件が発生します。
弊社では、その点検に付随して発生する関連工事まで一貫して対応いたします。
年間200件を超える点検と、150件を超える工事実績に基づいた知識と技術と経験で、お客様のご要望にお応えします!
水処理設備のオーバーホールをご検討の際は、ぜひ一度エスプラントサービスまでご相談ください。貴社設備の現状を診断・分析し、最適解をご提案いたします!
そのほかにも、定期点検や修繕工事、アフターサービスまで、お客様のご要望に合った充実したサービス内容をご提案させていただきます。
▽関連記事を読む▽
≫排水処理設備の「見えないリスク」をなくす:そのトラブル、本当に“突然”でしたか?
≫排水処理設備の耐用年数と交換の重要性
▽関連ページ▽
≫エスプラントサービスの事業内容を詳しく見る
≫エスプラントサービスの強みもご覧ください


